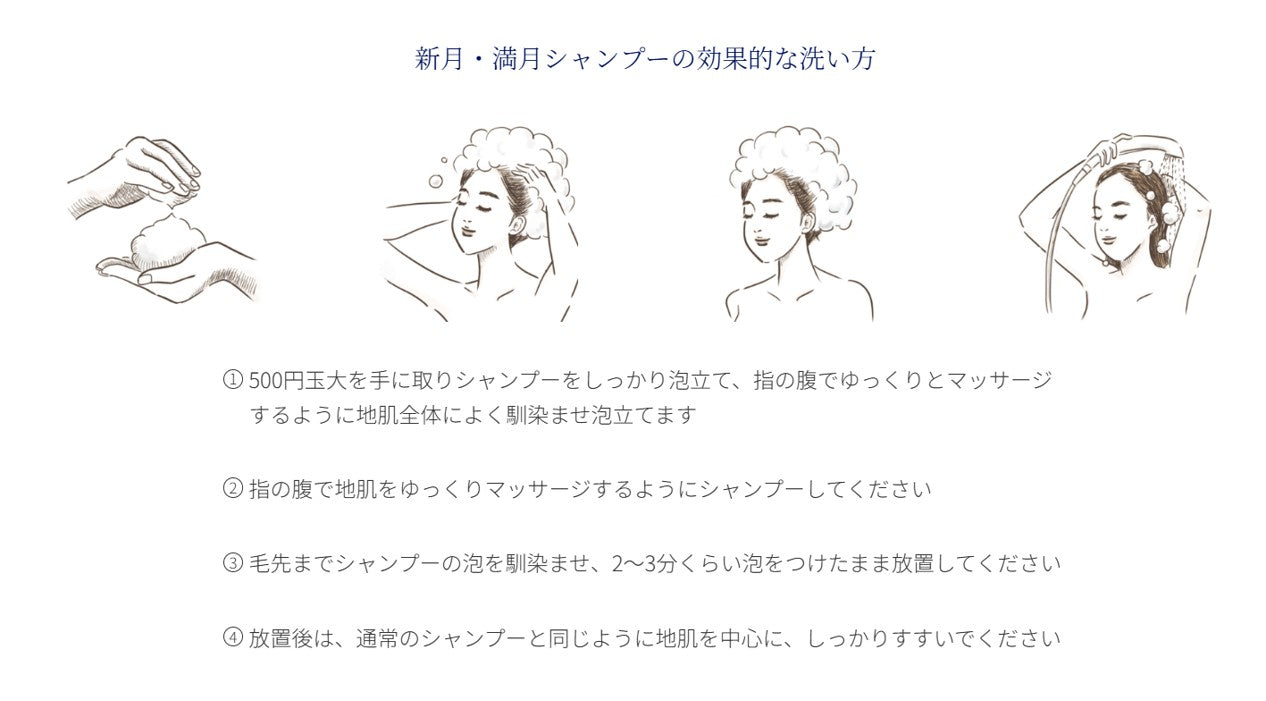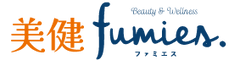健康診断の結果が気になる方の毎日対策-血圧・コレステロール-
──パレオケトジェニック的なアプローチで、無理なく整える──年に一度の健康診断。血圧やコレステロールの数値に「ちょっと気になる…」という方は多くいらっしゃいます。
大切なのは、毎日の食事や習慣を少しずつ見直し、体が本来のバランスを忘れられるような環境を整えること。
【血圧編】
「減塩=正解」とは限らない? 塩分に関する誤解を見直す
従来、血圧対策と言えば「減塩」が強く推奨されてきましたが、最近ではミネラルバランスの観点から、極端な減塩はかえって健康を損なう可能性があることが指摘されています。
たしかに、過剰なナトリウム摂取が血圧に影響する可能性があることは事実です。ただし、ここで問題とされているのは、ナトリウム(塩化ナトリウム)のみを含む「精製塩」です。
本来の“塩”とは、ナトリウムだけでなく、カリウム・マグネシウム・カルシウムなどの天然ミネラルを豊富に含んだ、海塩や岩塩といった自然の塩を指します。
これらの天然塩に含まれるミネラルは、体内の電解質バランスを整え、血圧の安定にも貢献すると考えられています。
また、腎臓機能が健康的な方であれば、体は余分なナトリウムを尿や汗として自然に排出する仕組みを備えており、質の良い塩を適度に摂ることは、むしろ健康維持に必要であるという見解も近年注目されています。
ココナッツオイルで「整う体」をサポート
実際に、ココナッツオイルを毎日の食生活に取り入れている方の中には、血圧が安定してきたという声も少なくありません。
もちろん、特定の食品が直接数値を下げるわけではありませんが、ココナッツオイルに含まれる中鎖脂肪酸(MCT)は、代謝サポートや体重管理、血糖バランスの改善に役立つとされており、それらの変化が体全体のバランスを整える結果として、血圧の安定につながっていると考えられます。
また、ココナッツオイルは抗酸化作用や腸内環境への好影響も期待されており、「脂質=悪」と決めつけない、柔軟な食事選びの一例として取り入れる価値のある食品です。

【コレステロール編】
「悪玉」という呼び方の誤解にご注意を
近年、健康診断の項目で気になる方が多い「コレステロール」ですが、現在ではその役割や捉え方について、以前とは少し異なる見解も出てきています。
健康診断で「悪玉コレステロール(LDL)」という言葉を目にすると、不安に感じる方も多いかもしれません。
けれども、LDLコレステロールは本来、体にとって必要な働きを持っている存在です。
LDLは、コレステロールを肝臓から全身に運び、細胞膜やホルモン、ビタミンD、胆汁酸などを作る材料として不可欠なものです。
一部では「悪霊」のように扱われがちですが、すべての人にとって“排除すべきもの”というわけではなく、むしろ適切な量が必要な大切な栄養素です。
そのため、近年の研究では、LDLの値が極端に低すぎると、免疫機能や神経機能のバランスが崩れるリスクがあり、寿命に関係することも示唆されています。
コレステロール管理は「とにかく下げる」ことよりも、“バランス”や“質”を整えることが大切だと考えられています。
たとえば、
-
中性脂肪(TG)との比率
-
HDL(善玉)とのバランス
-
酸化LDLや粒子のサイズ(小型LDLなど)
といった要素も合わせて総合的に見ていくことが、より的確な判断につながります。
肝機能の正常化がコレステロールバランスの鍵に
コレステロールのバランスを考えて、肝臓の働きは見落とせない重要なポイントです。実は、LDLコレステロールの約70〜80%は、食事からではなく、体内-肝臓で合成されていることが知られています。
肝臓は、
-
コレステロールの合成
-
血中への放出(VLDL→LDL)
-
LDLの回収(受容体での再取り込み)
-
胆汁への排出(コレステロール排出)
といったプロセスを担っており、肝機能が健全であることが、コレステロールの“つくる・運ぶ・処理する”の全体バランスを支えています。
そのため、肝臓が疲れていたり、脂肪肝などの負担を抱えていたりすると、LDLの合成過多や排出不足が起こり、数値が乱れやすくなることがあります。
コレステロール値が気になるために、食事の見直しだけでなく、
-
アルコールの摂り方
-
加工食品やトランス脂肪酸の摂取量
-
睡眠・ストレス・血糖のバランス
といった肝臓にやさしい生活習慣の見直しも意識してみると良いでしょう。
肝機能を整えるために心がけたい食習慣と生活のヒント
(特にお酒を飲む方へ)
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、多少のダメージがあっても自覚症状が出にくい臓器です。だからこそ、普段からのケアが大切です。
とくにお酒をよく飲まれる方は、知らず知らずのうちに肝臓に負担をかけていることがあります。
アルコールと肝臓の関係
アルコールは肝臓で分解されますが、このときアセトアルデヒドという有害物質が一時的に発生します。この代謝過程で肝臓には強い酸化ストレスがかかるため、解毒や修復にエネルギーと栄養が大量に消費されます。
さらに、アルコールの摂取が続くと脂肪肝や炎症が進行し、LDLの代謝にも影響が出るため、コレステロール値が乱れやすくなる傾向があります。
肝臓に優しい食材(お酒の飲み方にもおすすめ)
-
しじみ・あさり:オルニチン、タウリンが豊富
-
納豆・味噌・漬物などの発酵食品:腸から肝臓への負担を軽減
-
ブロッコリー・キャベツ・カリフラワーなどのアブラナ科野菜:解毒酵素を活性化
-
アボカド・オリーブオイル:肝臓に優しい良質な脂質
-
緑茶・ウコン(過剰摂取に注意):抗酸化サポート
控えたいもの
-
トランス脂肪酸(マーガリン、ショートニング)
-
砂糖・果糖の多い清涼飲料水やお菓子
-
加工食品・添加物の多い食事→これらは肝臓での解毒・処理に負担がかかり、脂肪肝の原因にもなります。
まとめ
健康診断の数値に一喜一憂するよりも、「体がどうすれば本来のバランスに戻れるのか?」という視点で、毎日の暮らしを見直していくことが大切です。
私たちの体は、整った食事、良質な脂質、適度な運動、心地よい睡眠によって、ゆっくりと変わっていきます。数値を「下げる」のではなく、「整える」ことで結果的に改善されるという視点で、無理なく、心地よく、日々を整えていきましょう。
塩分を見直す──「減塩」よりも「質の良い塩」にシフト
精製塩(NaClのみ)ではなく、天然の岩塩や海塩など、マグネシウムやカリウムを含む自然塩を適量摂ることで、体内の電解質バランスが整い、血圧の安定につながります。腎機能に問題がない限り、余分なナトリウムは尿や汗として排出されます。
カリウムやマグネシウムをしっかり摂る
カリウムは体内の余分なナトリウムを排出し、血圧を調整するミネラルです。
また、マグネシウムは血管の収縮を抑え、自然な降圧作用をもたらします。
おすすめ食材:
-
カリウム:アボカド、ほうれん草、キウイ、※里いも、バナナ(糖質には注意)
-
マグネシウム:アーモンド、ひじき、玄米、ダークチョコレート(砂糖不使用、もしくはGI値の低いミネラル豊富な甘味料使用)
食物繊維と発酵食品で腸から健康に
食物繊維は塩分や脂質の吸収をゆるやかにし、血糖値の急上昇を防ぎます。
また、パレオ的な視点では、腸内環境の改善はすべての健康の土台。
味噌、ぬか漬け、納豆などの発酵食品を取り入れることも血圧・脂質対策に有効です。
良質な脂質を積極的に摂取
コレステロール値が気になる方こそ、「脂質=悪」と誤解しないことが重要です。
EPA・DHAを多く含む青魚(サバ、サンマ、イワシなど)や、オリーブオイル、アボカドナッツ類などの抗炎症作用を持つ脂質を意識的に取りましょう。トランス脂肪酸や酸化油を避けることも基本です。
パレオケトの・おすすめの運動習慣
現代人の慢性炎症や代謝異常は、運動不足と慢性的なストレスが大きな課題です。激しい運動よりも、日常の中で無理なく続けられる軽い運動や自然な身体活動が継続のカギです。
-
やウォーキング散歩(毎日20〜30分)
-
スクワットや階段昇降などの軽負荷筋トレ
-
深呼吸を意識したストレッチ・ヨガ
※疲れな有酸素運動は一時的にコレステロール値を上げることもあり、そのために疲れを感じない範囲で行うことが推奨されます。
毎日の生活で気をつけたいポイント
-
体重管理は「糖質制限+良質脂質の導入」が効果的
血圧や中性脂肪、LDL値が気になる方は、カロリーよりも糖質の量と質を見直すことが重要です。 -
アルコールと喫煙の見直し
アルコールは「適量」であればリラックス効果がありますが、糖質を含まない焼酎やウイスキーなどを選ぶのがおすすめです。 喫煙は動脈硬化の大敵なので禁煙を目指しましょう。 -
睡眠・ストレスケアも重要
睡眠不足や慢性ストレスは自律神経を乱し、血圧上昇の一因に。自然なリズムで早寝早起きを意識し、夜のスマホやカフェインは控えましょう。
具体的な1日の食事例(パレオケトジェニック対応)
朝食
-
目玉焼き or ゆで卵(良質な脂質というぱく質)
-
アボカドとナッツのサラダ(マグネシウム+脂質+食物繊維)
-
味噌汁(わかめ、豆腐入り)
昼食
-
鯖の塩焼き
-
ほうれん草のおひたし、発酵漬物
-
雑穀や玄米 少量(糖質制限レベルに応じて)
夕食
-
サーモン or イワシのカルパッチョ
-
きのこ・海藻スープ
-
カリフラワーライス or 糖質制限麺(空腹時の調整に)
改善を感じるには最低3ヶ月
体質改善には最低3ヶ月以上の継続が必要です。かなり少なくなり、「足し算から始める」ことが習慣化の始まりです。まずは良質な塩、脂質、食材を「足す」から始めてみてください。数値の変化は、3ヶ月〜半年後の健康診断で「未来の自分」が教えてくれます。
Related Posts

24時間乾かない! 乾燥肌・敏感肌の救世主アイテム特集
乾燥崩れ・粉吹き・つっぱり知らず! 朝から夜まで潤い続ける秘訣を教えます なぜ私たちは“保湿しても乾く”のか? 「しっかり保湿しているはずなのに、夕方になると肌がつっぱる…」 そんな悩みを抱えている方は、実は少なくありません。原因は単に「乾燥している」だけではなく、肌の内側にある“バリア機能の乱れ”や、保湿の“質”の不足にあります。 肌は外側から見ると滑らかに見えても、その内部では「水分を保持する力(角質細胞間脂質)」や「外的刺激を防ぐバリア機能」が絶えず働いています。特にこのバリア機能が低下すると、せっかく補った水分や美容成分もどんどん蒸発してしまうのです。 さらに多くの人がやってしまいがちなのが、「とりあえず化粧水だけつける」「ベタつくのが苦手で乳液を省く」などの**“保湿ステップの簡略化”**です。 これでは一時的に潤ったように感じても、肌の深層には十分に水分が届いていない可能性があります。 また、肌が乾燥していると「もっと保湿を」と思いがちですが、過度な塗布や頻回なミストの使用も逆効果になることがあります。肌が本来持っている自ら潤う力(バリア再生機能)を弱めてしまう可能性があるからです。 つまり、「量」より「質」。肌に本当に必要なのは、外側からの水分補給だけでなく、肌本来の働きをサポートする保湿成分や生活習慣の見直しです。 本記事では、朝から夜まで乾かずに過ごすために必要な「潤いを逃がさない」スキンケア術を、美容感度の高いアラサー女性の視点からご紹介していきます。 後半では美健fumiesがおすすめする、成分や使用感にこだわった厳選アイテムも登場しますので、ぜひ最後までご覧ください。...
続きを読む
目指すはマイナス5歳肌! スキンケア迷子に贈る“再出発”マニュアル
【変化の正体】40代の肌に起こる「たるみ」の原因とは? 「なんだか最近、顔全体がぼやけてきた気がする」「昔より口角が浮かんで見える」──...
続きを読む