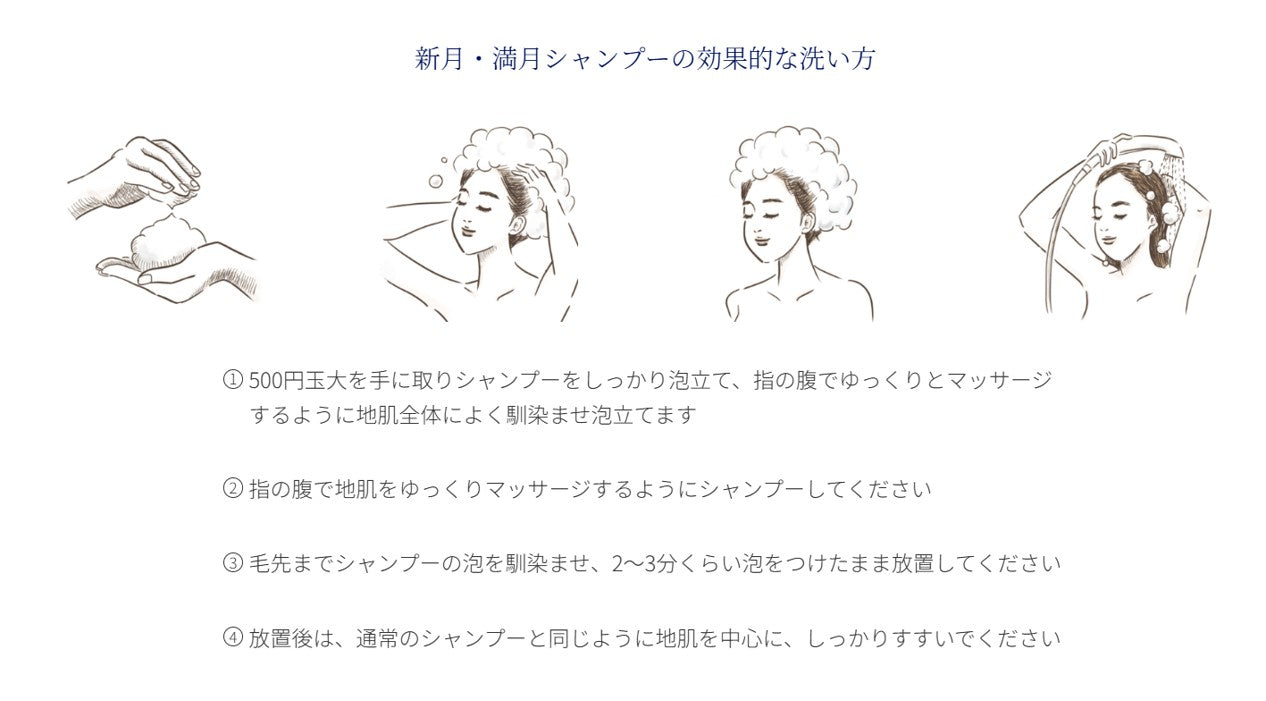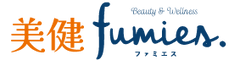フィルター
10 製品
-
並び替え

生活習慣を見直し腸内環境を整える
食事・運動・睡眠を整える
腸内環境は非常に繊細で何か一つを頑張って整えるというより全体的に整えることが必要とされます。体質により効果的な対策も違うので悩んだらお気軽に問合せてください。
商品選びに迷ったら
美健ファミエスではお客様のお話を元に、専門知識を持ったスタッフがおすすめの所品をご提案しています。毛髪検査等でお客様独自のパーソナルメニューを作成することもできます。
体質改善したい方への情報

消化・免疫・代謝を整えて、体質改善へ
──日々の食と暮らしを、家族の未来のために── 「最近、アレルギーがひどくなった気がする」「子どもや親の健康のために、何か始めたいけれど何が正解かわからない」 そんな思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。 アレルギー、慢性的な疲れ、冷え、肥満、肌荒れ、風邪をひきやすい体質…。こうした症状の背景には、「体内の土台機能」がうまく働いていないことが少なくありません。 それが、消化・免疫・代謝です。この3つはそれぞれ独立した働きではなく、密接に連携し合い、健康のバランスを支えています。 「消化・免疫・代謝」とは?まずは体の“土台”を知ることから ● 消化とは 食べたものを分解し、体が使える栄養素として「吸収」するためのプロセスです。胃酸・消化酵素・腸内細菌などが連携して働き、私たちはエネルギーや材料を得ています。しかし、加齢・ストレス・加工食品の摂取・早食いなどが影響し、うまく消化できていない人も少なくありません。 消化の不調は、栄養不足や腸の炎症、免疫低下、代謝の乱れなど、多くの不調の入り口になる重要なポイントです。 ● 免疫とは ウイルスや細菌、有害物質から体を守る防御システムであり、がん細胞など体内の異常もチェックし、排除する役割を果たしています。免疫が適切に働いていれば、風邪をひきにくくなったり、アレルギー反応も抑えられやすくなります。 また、腸には免疫細胞の約70%が集中しているとされ、 “腸内環境=免疫力”ともいえるほど、消化機能と深く関わっています。 ...
続きを読む
腸活とは? 健康を司る「第二の脳」を整える
──毛髪・遺伝子検査も活用した、自分に合った毎日対策── 最近、「なんだか毎朝すっきりしないな…」と感じていませんか?年齢を重ねるごとに、体の巡りやお腹の調子に変化を感じる方は少なくありません。特に40代以降は酵素の働きが著しく衰えてしまうことに加え、忙しい日常や食事の乱れ、睡眠不足、ストレスなどが積み重なり、腸の働きにも影響を与えることがあります。そんな中、今あらためて注目されているのが「腸内環境を整えること=腸活」です。 腸は単なる消化器官ではなく、“第二の脳”とも呼ばれるほど、心と体に密接な影響を持つ臓器。 消化吸収はもちろん、免疫力やホルモン分泌、さらにはメンタルバランスにも関わっていることが、数多くの研究で明らかになっています。 最近では、NHKなどのテレビ番組でも、腸内フローラと健康・美容・加齢臭・肥満との関係が取り上げられ、ますます注目が高まっています。 とはいえ、「何が本当に腸に良いのか?」については、まだ誤解や思い込みも多く、情報が錯綜しているのが現状です。 なぜ「腸」は“第二の脳”と呼ばれているの? 実は腸には、脳とは独立して働く「腸管神経系(Enteric Nervous System)」という神経ネットワークが張り巡らされています。この神経の数は、なんと脳に次いで多い約1億個以上とも言われ、腸が自律的に判断し、活動する力を持っていることから、 “第二の脳”という名前で呼ばれるようになったのです。 さらに近年では、腸と脳が相互に影響し合う「腸脳相関(gut-brain axis)」という考え方も注目されており、腸の状態が不安定になると、気分が落ち込んだり、イライラしやすくなることが科学的にも明らかになってきました。 たとえば、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの約90%が腸でつくられているというのも有名な話です。※ただし、脳で働くセロトニン(神経伝達物質としてのセロトニン)は、脳内で合成されたものであり、腸で作られたものが直接脳に届くわけではありません。つまり、腸のコンディションは、体調だけでなくメンタルや感情の安定にも深く関わっているということなのです。 「ヨーグルトを食べれば腸にいい」は本当? 腸に良い食品として真っ先に挙がるのがヨーグルトですが、その常識に一石を投じたのがNHKスペシャルで紹介された「通過菌」の話です。...
続きを読む
巡りを整え、芯から温まる 大人の温活対策
──毛髪・遺伝子検査と“電子・水素”の力を活かして、体の内側から巡りをサポート── 「手足が冷えて眠れない」「お風呂に入ってもすぐ冷える」そんな“芯から冷える”感覚に悩まされていませんか? 冷えは、年齢を重ねるごとに多くの人が感じやすくなる不調の一つです。特に40代以降は、ホルモンバランスの変化や筋力の低下、血行の悪化などが重なり、体の“巡り”が滞りがちになります。 さらに、忙しい日々の中での食事の乱れ、ストレス、睡眠不足なども影響し、「体の芯が冷えている」「なかなか疲れが取れない」と感じる方が増えています。 「温める」だけでは、冷えは改善しない? カイロや靴下などで外側から温める方法もありますが、それだけでは「その場しのぎ」に終わりがちです。 冷えの背景には、実は以下のような複合的な原因が関係しています ミネラル不足による血流の悪化 自律神経の乱れによる末端冷え 筋肉量や基礎代謝の低下 甲状腺やホルモンバランスの影響 とくに見落とされがちなのが、加齢による筋肉量の低下。40歳を過ぎると、何もしなければ年間およそ1%ずつ筋肉量が減少すると言われており、筋肉による熱産生が衰えることで、冷えやすい体質になってしまいます。このような状態は「サルコペニア(加齢性筋肉減少症)」と呼ばれ、基礎代謝の低下、血流の悪化、慢性的な冷えの大きな原因となります。また、筋肉を維持し、冷えにくい体をつくるには、適度な運動だけでなく、日々のタンパク質摂取がとても重要です。タンパク質は筋肉の材料であると同時に、血液やホルモン、免疫機能の維持にも重要な役割を果たしています。炭水化物が中心になりがちな現代の食生活では、非常に不足しやすい栄養素の一つでもあり、とくに間食での工夫が冷え対策にも大きく影響します。 体温と病気の関係 ──「35℃台」が続くと、病気にかかりやすくなる? 体温は健康のバロメーターです。健康な成人の平熱は一般に36.5~37.0℃とされていますが、近年では「35℃台が当たり前」という方も珍しくありません。 しかしこの状態が続くと、以下のような影響が懸念されます 免疫力の低下(NK細胞などの働きが鈍くなる) 酵素活性の低下(消化・代謝・解毒などの効率が落ちる)...
続きを読む